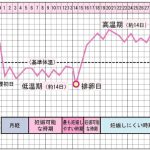[PR]二階堂支配人がおすすめする出会えるサイトはこちらになります!(18禁)

エロとは、「エロチシズム」あるいは「エロチック」の略とされ、「わいせつなこと」また、「そのさま」を表す言葉だとされています。また、「エロティカ」という言葉がありますが、これは、エロティシズム(色情)を刺激したり性的興奮を起こしたりする官能的な描写を扱う文学(性愛文学・官能小説・好色文学)・写真・映画・絵画(春画など)・彫刻などの芸術作品を指します。
エロティカは、人間の肉体や性を、芸術的な意図やハイアートを制作するという抱負とともに描く作品を指す近代の用語で、商業的・金銭的な意図から制作されるポルノグラフィとは別とされます。
一般的には、「エロティカ」は、性的興奮を起こす素材を扱う作品のうち、芸術的・科学的な価値を意図したり残したりしているものを指し、「ポルノグラフィ」は、性を好色に描写し芸術的価値が少ないか全くないものを指します。ただし、エロティカとポルノグラフィ(あるいは性的娯楽作品)との違いを区別することは、非常に難しいです。
エロティカは性的な面白さより芸術的な面白さを追求するものであり、それゆえにポルノとは違うとされます。しかし、エロティカも実際は性的興奮を起こすことを目的としているという意見もあります。一方では、金儲けを目的としたポルノが、裸体芸術や性科学などの名目で公開されてきた歴史もあります。他方では、商業的目的で製作され、性を商業化するものとして糾弾されることのあるピンク映画などのポルノ映画やヌード写真の中には、制作者の作家性を見出され芸術作品として評価されるものもあります。
エロとポルノとを区別することが可能かどうかという問題は、多くの複雑な疑問を生んでいます。例えば、作品から起こされる美学的な感情と官能的な感情は互いに独立したもので切り離せるものかどうか、作品内の芸術性や商業性の度合いを客観的に計ることができるかどうか、どの時点で作品はポルノと呼ばれるのかどうか、などがあります。
こうしたことから、性を描いた小説や写真・映画などが、税関で没収されたり、上映・出版・展覧に反対運動が起きたり、禁止の措置が下されたりするようなことがありました。そして、その作品を享受されるべき芸術作品とするか、享受されるべきでないわいせつ物とみるかで、様々な裁判や事件が発生してきました。
裸婦像は、ルネサンス以後のヨーロッパではギリシア神話などに仮託して描かれてきましたが、しばしば弾圧や破棄の対象となってきました。17世紀のスペインでは裸婦像は禁じられ、異端審問所による没収や画家の処罰が行われました。裸婦を描くことが比較的自由であったフランスでも、ヌードを描いたレオナルド・ダ・ヴィンチの「レダと白鳥」が破棄されるなどの事件が起きています。
19世紀のヨーロッパでは、ヌード絵画や彫刻が宮廷から市民社会へと進出しましたが、その過程で様々な抵抗を受けました。イギリスでは、ギリシャ・ローマといった古典古代への関心の高まりなどからヌードへの関心が高まりましたが、一方で宗教や道徳あるいは社会改良の立場からヌードやわいせつ物が攻撃されました。特に1857年の猥褻出版物取締法制定後には、どこからが芸術でどこからがわいせつかという区別が論争の種になりました。1885年にはロイヤルアカデミーなどへのヌード絵画の出品が目に余るとする匿名の婦人が「タイムズ」に投書を寄せ、ヌード作品により観客は気分を害され、しかも若い女性がヌードモデルとなることで観客の好色の目にさらされ堕落する危険があるとして展覧会のボイコットを訴えました。これに対し、多くの新聞を舞台に芸術家と運動家との間でヌード作品の存在意義をめぐる論戦が起きました。
日本では明治以降、ヨーロッパからヌードデッサンが芸術教育に採り入れられましたが社会の抵抗は大きく、初期の裸体画、例えば黒田清輝の『朝妝』(ちょうしょう)は未成年閲覧禁止措置が取られました。また第二次世界大戦後には『チャタレイ夫人の恋人』の翻訳出版をめぐるチャタレー事件、『四畳半襖の下張』の雑誌掲載をめぐる四畳半襖の下張事件などが起きています。
エロに対する捉え方は人様々です。エロを芸術として捉える人たちは、「エロとはアートでありカルチャー」です。そうでない人たちにとって、「エロは卑猥」なのです。エロの捉え方は、裸を見て「卑猥だ」と思うか「美しい」と思うかの違いです。エロい物体が陳列されている秘宝館や、様々なバイブが展示されているバイブバーに行った時に、「昔はこんな文化があったんだ」「アダルト産業のモノづくりはすごいなぁ」と思う人もいれば、「下品、汚い」「いやらしい」と感じる人もいます。
ラブドール(女性の等身大人形)についても、当初は性処理だけが目的の単なる「ダッチワイフ」でしたが、昨年開催された製造元であるオリエント工業のラブドール展には、若い女性客が多くて来ていたそうです。女性客らはラブドールを見て「かわいい」「きれい」「下着がおしゃれ」と言いながら盛り上がっていたそうです。このことは、ラブドールが単なる「卑猥な性玩具」としてではなく、ひとつの芸術作品として受け入れられている証拠とも言えるでしょう。
いっときはタブーとして人の目から遠ざけられていた「春画」。近年の再評価によって多くの人が存在を知り、作品に触れる機会が増えました。2015年から2016年にかけて東京の永青文庫と京都の細見美術館で開かれた春画展は、東京だけでも21万人以上が来場する人気ぶりだったとか。来場者の約六割を占めたのは女性たちで、国内で毀損されてきた春画の価値を再評価する機運は高まっています。
次回は、春画について、書いてみたいと思います。